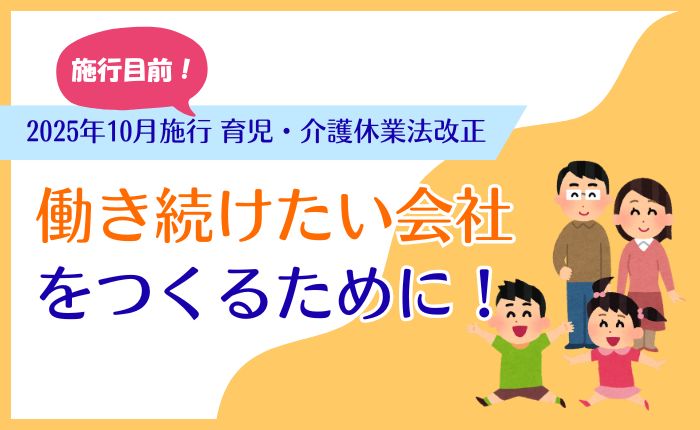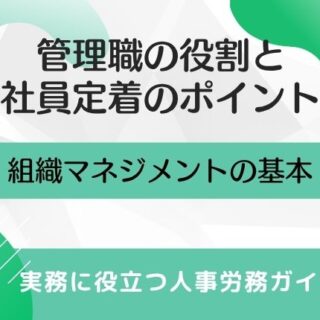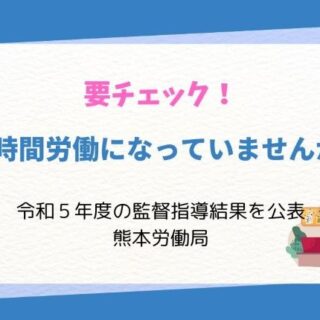はじめに
少子高齢化が進み、共働き世帯が増加する中で、育児や介護を理由に仕事を辞めざるを得ないケースは少なくありません。
こうした離職を防ぎ、誰もが安心して働き続けられる社会を実現するために、企業にはライフステージに応じた柔軟な働き方の提供が求められています。
この背景を踏まえ、育児・介護休業法が改正され、2025年4月から段階的に施行されています。
そして10月1日からは改正法の第二段階がスタートし、企業に新たな義務が課されます。
今回の記事では、施行直前の今だからこそ確認しておきたい改正内容と、企業が取るべき準備について詳しく解説します。
単なる法対応にとどまらず、「従業員が安心して働き続けられる職場づくり」という観点で取り組むことがポイントです。
法改正の背景と趣旨
少子高齢化と共働き世帯の増加
日本では少子高齢化が急速に進み、人口減少が加速しています。
それに伴い、共働き世帯は増え続け、子育てや介護と仕事の両立は、多くの従業員にとって身近な課題となっています。
こうした社会の変化に対応するため、企業にはライフステージに関わらず、従業員が希望に応じて働き続けられる職場環境の整備が求められています。
「義務だから整える」ではなく「離職防止と人材確保」のために
今回の改正は、単に法律を守るために制度を整備するだけではなく、
育児や介護を理由とした離職を防ぎ、優秀な人材を確保することにもつながります。
特に、出産・育児を予定する時期から、子どもが3歳を過ぎて就学するまでの長い期間にわたり、
従業員が柔軟に働ける制度を提供することで、仕事と家庭の両立を支援します。
企業が前向きに制度を活用することで、結果として採用力・定着率の向上にもつながるのです。
10月施行のポイント
今回の改正は2025年4月と10月の2段階で進められていますが、
10月1日からは特に次の3つが大きなポイントになります。
1. 「3歳~就学前」の子を育てる従業員への柔軟な働き方支援
企業は以下の5つの選択肢から2つ以上を選び、制度として整備することが義務化されます。
従業員は、その中から自分に合った1つを選んで利用できます。
-
始業・終業時刻の変更(時差出勤やフレックスタイムなど)
-
テレワーク制度(月10日以上の利用が可能な制度)
-
保育支援(保育施設の設置・運営やベビーシッター費用補助)
-
養育両立支援休暇(年10日以上、原則時間単位で利用可能)
-
短時間勤務制度(所定労働時間を短縮できる制度)
これまでの多くの制度は「3歳未満」までが対象でしたが、
今回の改正で「小学校就学前」まで対象が拡大されます。
制度選びのポイント:現場の声を必ず聴く
制度を整える際は、企業側が一方的に決めるのではなく、職場のニーズを正しく把握することが重要です。
-
過半数労働組合等(ない場合は過半数代表者)への意見聴取は義務
-
さらに、育児当事者から直接困りごとやニーズを聞くことが望ましい
これは、制度が「形だけ」にならず、実際に活用される仕組みにするために欠かせないステップです。
2. 個別周知と意向確認の義務化
制度を整備するだけではなく、従業員への個別周知と意向確認も義務化されます。
-
対象期間:子どもが1歳11か月~2歳11か月の間
-
内容:制度の内容を個別に説明し、どの制度を利用したいかを確認する
単なる一斉通知ではなく、一人ひとりと対話しながら進めることが求められます。
3. 仕事と育児の両立に関する意向聴取・配慮
さらに、従業員の子が3歳になるまでの適切な時期に、
仕事と育児の両立に関して個別に意向を聴取し、可能な限り配慮することが必要です。
これは、先ほどの「個別の周知・意向確認」とは別の制度です。
確認すべき項目は以下の4つです。
-
勤務時間帯(始業・終業時刻)
-
勤務地(就業場所)
-
制度利用の期間
-
就業条件(業務量や労働条件)
従業員の希望を把握し、実際の働き方に反映させることで、安心して働き続けられる環境づくりにつながります。
10月施行までに整えておきたいこと
10月施行に向けて、企業が今すぐ取り組むべき準備をまとめました。
-
自社で整備する「2つ以上の制度」を決定
-
就業規則や社内ルールへの反映
-
対象者への周知スケジュールの確認
-
面談担当者の決定と社内研修の実施
施行日直前ではなく、計画的に準備を進めることがポイントです。
まとめ:制度整備は「義務対応」で終わらせない
今回の改正は、単に法律で決められたことを守るためではありません。
企業が職場環境を見直し、従業員が働き続けたいと思える会社づくりを進めるきっかけです。
柔軟な働き方の制度を整えることは、結果的に採用力の向上や人材定着にもつながる投資といえます。
このタイミングでしっかりと準備を進め、10月1日を迎えましょう。
制度運用に役立つマニュアル
今回の制度運用に役立つマニュアルが、厚生労働省から公開されています。
制度導入から運用までの流れがわかりやすく解説されているので、ぜひご活用ください。