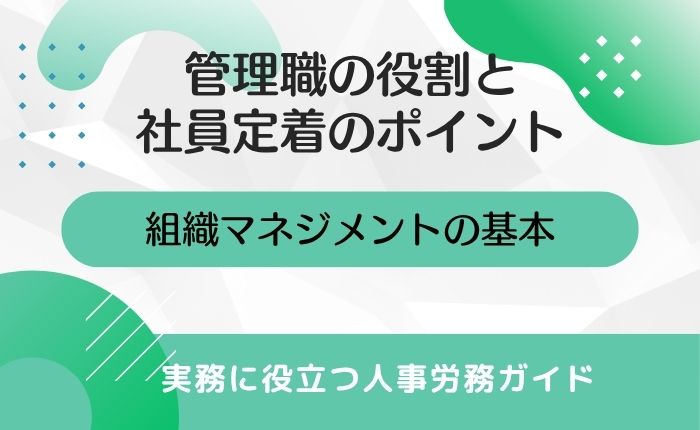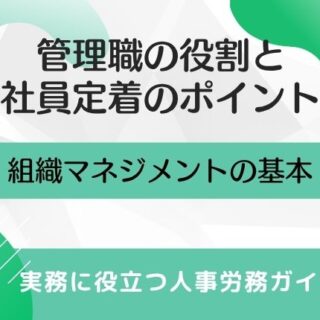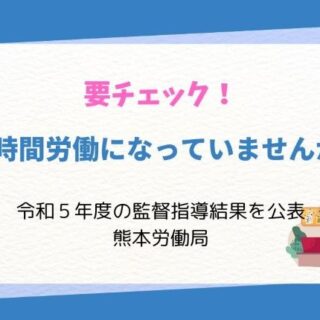企業におけるマネジメントには大きく分けて二つの対象があります。
1つは部下一人の成長を促すことを目的とした「育成マネジメント」、
もう1つは組織全体を動かすことを目的とした「組織マネジメント」です。
両者は似ているようで大きく異なり、特に中小企業では、管理職の役割分担や社員定着に直結する重要なテーマとなります。
部下育成と組織マネジメントの違い
部下のやる気を維持することを目的としたマネジメントのポイントは以下の通りです。
・その人にあった難易度の課題を与える
・やる目的や具体的なやり方等を説明する
・状況に合わせて課題を変化させる
つまり、育成マネジメントでは「目的」「やり方」「裁量範囲」まで細かく伝えることが有効です。
しかし、組織を動かすことが目的とした場合は、
このようなやり方は逆にやってはいけないマネジメントとなります。
組織マネジメントでは、細かい指示は途中で解釈がずれやすく、混乱を招く
いわゆる「伝言ゲーム」が発生し、現場に届く頃にはニュアンスが変わってしまいます。
骨太な方針が組織を動かす
組織全体を動かすカギは、「骨太な方針」です。
「何を目指すのか」だけをシンプルに示し、「どうやるか」は現場に委ねるのが原則です。
例えば、
-
「安全第一で行動する」
-
「顧客満足を高める」
これらは誤解の余地がなく、誰が聞いても同じ方向性を理解できます。
組織を動かすための指示、つまり「骨太な方針」の特徴は、「何をやるべきかだけ」を指示することです。
管理職の役割と社員定着
骨太な方針を具体的な行動に変換するのは管理職の役割です。
課長やリーダーは現場の特性を理解しているため、方針を実行可能な計画へ落とし込みます。
経営者が細部まで指示を出すと、かえって士気低下や離職につながるケースもあります。
逆に、役割分担が明確な組織は、社員が安心して働ける環境となり、社員定着率の向上にも直結します。
組織マネジメント実践の流れ
組織を動かすマネジメントの流れを整理すると、以下のようになります。
-
経営者が骨太な方針を示す
-
骨太な方針を受け取った管理職やリーダーは、自分の専門性や部署の特性を考えて肉付けをする。
-
さらに部下に、「骨太で簡単明瞭な指示」になるように、管理職やリーダーが現場に噛み砕いて伝える
-
社員が実行に移す
この流れを確立することで、組織全体が一貫した方向性を保ちながら動ける体制が整います。
まとめ
組織マネジメントの基本は「骨太な方針」を掲げ、経営者は方向性、管理職は具体策、社員は実行という役割を明確にすることです。
これにより、組織の安定と社員の定着につながり、強くて活力ある職場づくりが実現できます。