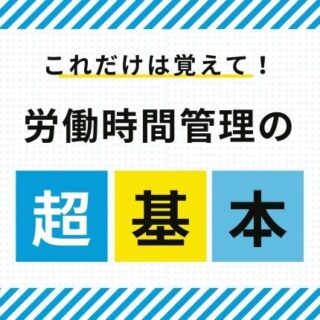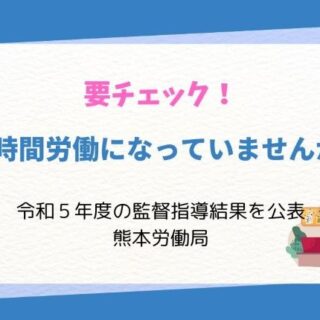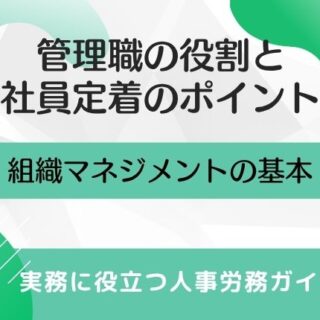今回は 「パワーハラスメント(パワハラ)」 について、企業の経営者や人事労務担当者の方向けに、厚生労働省から公開している『職場におけるハラスメント 対策パンフレット』を基に、最新の法規制を踏まえてわかりやすく解説します。
パワハラを未然に防ぎ、従業員が安心して働ける職場環境を整えましょう。
パワハラとは?
パワーハラスメントとは、職場での「優越的な関係」を背景に、業務の適正な範囲を超えて、相手に精神的・身体的苦痛を与えたり、職場環境を悪化させたりする行為を指します。
厚生労働省によれば、以下の3つの要素すべてを満たすものが「職場におけるパワハラ」に該当します。
-
優越的な関係を背景とした言動であること
-
業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動であること
-
その結果、労働者の就業環境が害されること
※出典:厚生労働省『職場におけるハラスメント対策パンフレット』
パワハラに該当する具体的な行為とは?
① 優越的な関係を背景とした言動
-
上司から部下への言動が典型例
-
部下が拒否・抵抗できない状況(専門知識を持つ同僚による圧力など)も該当します。
② 業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動
-
業務に必要な指導であればパワハラには該当しませんが、人格を否定する発言や過剰な叱責はNGです。
③ 就業環境が害される
-
精神的・身体的な苦痛により、業務に支障が出る場合が該当します。
6つのパワハラ類型と事例
厚生労働省は、パワハラを以下の6つの類型に分類しています。
- 身体的な攻撃
- 精神的な攻撃
- 人間関係からの切り離し
- 過大な要求
- 過小な要求
- 個の侵害
それぞれの具体例とともに見ていきましょう。
1.身体的な攻撃
暴力行為(殴る、蹴る、物を投げつける)
<事例>
A社では、上司が部下のミスに激高し、書類を机に叩きつけて「こんな簡単なこともできないのか!」と怒鳴った。部下は精神的に追い詰められ、休職を余儀なくされた。
② 精神的な攻撃
人格を否定する発言(「お前は無能だ」など)、執拗な叱責、みんなの前で罵倒
<事例>
B社では、新人社員に対し、上司が「お前のせいで会社の評価が下がる」「辞めたほうがいい」と繰り返し叱責。新人はうつ病を発症し、出社できなくなった。
③ 人間関係からの切り離し
仲間外れ や 無視、仕事を取り上げて孤立させる
<事例>
C社では、上司に意見をした社員が突然チームから外され、同僚からも無視される状態が半年以上続き、結果的に退職に至った。
④ 過大な要求
達成不可能なノルマ を課す、不必要な業務を強要する
<事例>
D社では、新人社員に対し、経験がないにも関わらず高度なプレゼン業務を任せ、結果が悪いと厳しく叱責。新人は自信を喪失し、退職した。
⑤ 過小な要求
役職に見合わない単純業務を与え続ける、仕事を与えない
<事例>
E社では、ある社員が異動後にまったく仕事を与えられず、1日中デスクに座っているだけの状態に。精神的苦痛を感じ、うつ状態となった。
⑥ 個の侵害
プライバシーの侵害(個人情報を許可なく暴露、私生活の監視)
<事例>
F社では、上司が部下の私生活に過度に干渉し、「彼氏と別れたの?」「不妊治療してるの?」などと繰り返し質問。部下は強いストレスを感じ退職した。
企業が取るべきパワハラ防止対策
パワハラを防ぐために、企業が講じるべき基本的な対策を紹介します。
- 明確なルールと周知の徹底
- 相談窓口を設置する
- 研修や教育を実施する
- 企業文化を見直す
1.明確なルールと周知の徹底
・就業規則やハラスメント防止方針を策定し、従業員に周知
・パワハラ行為に対する懲戒の方針を明文化
例)就業規則に「ハラスメントの定義」と「懲戒の基準」を具体的に記載する
ハラスメント防止方針を単独で文書化し、全社員に配布・説明する
② 相談窓口を設置する
・従業員が安心して相談できる窓口を社内・社外に設置
・匿名相談も可能にする
例)外部に匿名相談窓口を設置
③ 研修や教育を実施する
・管理職向けにハラスメント防止研修を定期実施
・実例を使ったケーススタディで理解を深める
例)管理職向け研修を定期(年2回など)に実施。
④ 企業文化を見直す
・「厳しい指導=指導力」という誤解を是正
・上司と部下のオープンなコミュニケーションを促す
例)定期的な1on1ミーティングを導入し、部下の意見を尊重する文化を育成など
まとめ
パワハラは、企業の 生産性の低下 や 職場環境の悪化 を招き、最悪の場合、法的責任 にもつながります。経営者・人事労務担当者としては、防止策をしっかり講じ、全員が安心して働ける環境を作ることが重要 です。
パワハラ対策は 「他人事」ではなく「会社全体の課題」。今すぐできることから始めていきましょう!