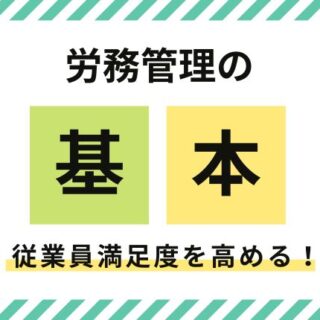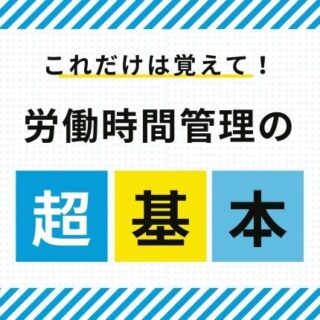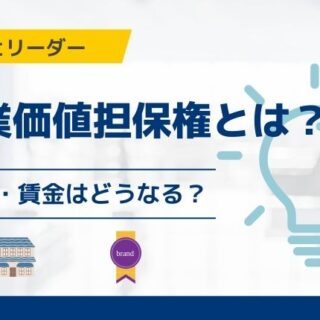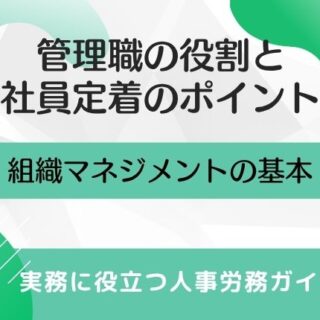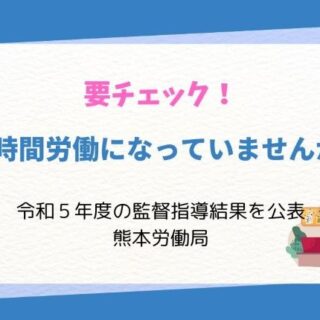知っているようで、知らない労務の基本について解説します。
今回のテーマは、「所定労働時間」と「法定労働時間」です。
「所定」と「法定」、その違いとは?
就業規則では、よくこのように規定してありますよね。
第●条 1日の所定労働時間は、8時間とする。
一方、労働基準法では、第32条には次のように書かれています。
(労働時間)
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
つまり、所定労働時間と法定労働時間とは、
「所定労働時間」・・・就業規則や、雇用契約書などで企業ごとに定めた労働時間
「法定労働時間」・・・労働基準法第32条で定められた労働時間(原則1日8時間、週40時間)の上限時間
です。※労働時間は、休憩時間は除いた時間になります。
では、所定労働時間は企業で定める労働時間だから、1日10時間、あるいは12時間など自由に決めていいかというとそうではありません。
労働基準法で定めた労働時間の上限時間、つまり1日8時間、週40時間の上限を超えて定めることはできません。※変形労働時間制を導入した場合を除く。
例えば、
始業時間 9:00 終業時間 17:45 (休憩時間60分) 週5日勤務
の場合、所定労働時間は1日7時間45分、週38時間45分になりますね。
法定労働時間の上限内であれば、1日の所定労働時間(勤務時間)を何時間にするかは、企業で決めることが出来ます。
1日所定労働時間(勤務時間)となっている企業は比較的多いようです。そうすると、法定労働時間の1日8時間と一緒ですよね。だから、混同してわかりづらくなっているのかもしれませんね。
会社で決めた労働時間が、1日8時間だと、法律で決められた労働時間と所定労働時間がたまたま同じ時間、というわけです。
では、「所定労働時間」と「法定労働時間」ってあまり気にしなくていいんですね?と思ったあなた!それは危険です。この違いってやっぱりちゃんと理解しておかないと大変なことになることがあります。
割増賃金について理解する!
所定労働時間と法定労働時間が一緒の場合は、あまり影響しませんが、所定労働時間<法定労働時間、つまり法定労働時間より所定労働時間が短い場合に気を付けて欲しいポイントがあります。
労務基準法第37条に以下のように定められています。
(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
割増賃金とは、法定労働時間を超えて労働をさせた場合、割増賃金の支払いをしなければなりません。
つまり、1日の所定労働時間が7時間30分で、ある日7時間45分勤務をした場合、法定労働時間の上限は越えていませんので、割増賃金の支払いは、法的には必要ありません。
ただ、企業の中には、法定の労働時間を超えていない残業時間に対して、割増賃金を支払っている企業があります。これは法律以上のことをしているので、従業員にとっては嬉しいことですし、何か問題があるわけではありません。
まとめ
所定労働時間と法定労働時間が違いを、ご理解いただけたでしょうか?
割増賃金の支払いについても、違いを理解して企業の経営戦略や経営方針として割増賃金を支払っているのか、違いを知らずに残業したから、ということで割増賃金分を支払っているのとでは違いますよね。
所定労働時間、法定労働時間については、労務管理上様々な場面で登場します。しっかり理解して、労務管理を行いましょう。
1ヶ月の変形労働時間制についての残業時間計算方法については、以下の記事をご覧ください。
1ヶ月単位の変形労働時間制の残業時間計算ってどうやって計算する?